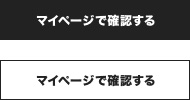【受発注】杉の下駄 ※4月中旬頃発送予定
快適に履ける杉の下駄
本受注会は終了いたしました。
年齢を重ねる中で着る機会が減ってきている浴衣。花火大会に夏祭り、そんな夏の特別なシーンに浴衣で行けたら素敵だなと思いながらも、また来年と見送ってしまっている方も多いかもしれません。SNSを活用して自分でもよりスムーズに浴衣を着られる今、日中の暑さを避けて夜に浴衣を着て出掛けてみたり、新たな浴衣とともに、今年は夏のお出かけを楽しんでみるのはいかがでしょうか。
染めの浴衣に合わせるシンプルな下駄
桐生織の産地である、群馬県桐生市で1919年に創業した桐染。2代目の山崎貞治さんは桐生織染色部門の伝統工芸士として、染色技術の発展と伝承に邁進しました。創業以来4世代に渡って培ってきた技術を使い、手染の魅力をプロダクトを通して伝えています。
染めの浴衣に合わせて作られたのが、杉の下駄。あえて染めずにシンプルな真っ白な鼻緒の下駄は、桐染の浴衣はもちろん、どんな浴衣にも合うので、1つ持っていれば重宝する一足です。
素材には木材のまちとして知られる、大分県日田市で採れた天然杉を使用。天然素材の為、木目が1点1点異なるという点も染めの浴衣と重なります。木目は焼くことで表面に凹凸が生まれ、履くと足裏との間に隙間が生まれます。その隙間と杉の高い調湿機能よって、暑い夏の日にも汗でベタっと張り付かず、快適に履けるのが特徴です。浴衣に合う涼しげで粋な下駄です。
手染めの魅力を伝える
1919年に群馬県桐生市で始まった桐染。桐生市は織物の産地として知られ、「西に西陣、東に桐生」と伝えられるように、桐生織には1000年以上の歴史があるのだそう。今でも、織物だけでなく縫製、刺繍等の製造工程の多くが営まれており、繊維産業が盛んな地域です。
桐染は明治後半から撚糸業を始め、1919年に初代山崎清四郎氏が染色業へと転進させました。以来、絹糸の色染めだけにとどまらず、生地染や製品染など時代のニーズに合わせて様々な染色を手掛けてきた染色工場で、2代目山崎貞治氏は桐生織染色部門の伝統工芸士として、染色技術の発展と伝承に邁進しました。2014年より屋号を桐染と改め、長く培ってきた技術による手染めの魅力を伝えたいという思いを、オリジナルブランドを通して発信しています。
| サイズ | 23〜25(cm) ※レディース |
| 重量 | 片足:約174g |
| 素材 | 鼻緒生地:綿100%
芯:ウレタン 台座:杉 |
| 生産国 | 日本 |
| 箱有無 | 無 |
商品特徴
-
◇大分県日田市の天然杉を使った下駄
◇木目を焼く事で凹凸ができ、足の裏と下駄の間にわずかな隙間が生まれる事で、快適な履き心地です。
受注会について
-
・受注期間:3月17日(日)〜4月1日(月)正午※在庫状況によっては早期に終了する場合がございます。
・お届け:4月中旬(一部商品は6月上旬)から順次発送予定
▼事前に必ず以下をご確認ください。
・不良品の場合を除き、受注会終了後のキャンセルや商品の返品・交換は承っておりません。
・お支払い方法は、【クレジットカード・アマゾンペイ・キャリア決済】のいずれかをお選びください。
・決済の都合上、発送前に決済確定を行う場合がございます。予めご了承くださいませ。
・今回の受注会のお品物は、他のアイテムとおまとめができません。お手数ですが、別でご注文いただきますようお願いいたします。また、配達日の指定はできません。
・在庫状況によってはキャンセルとさせていただく場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ブランド紹介
桐染(キリセン)
1919年に群馬県桐生市で創業した桐染(キリセン)。明治後半から撚糸業を始め、1919年に初代山崎清四郎氏が染色業へと転進させました。以来、絹糸の色染めだけにとどまらず、生地染や製品染など時代のニーズに合わせて様々な染色を手掛けてきた染色工場で、2代目山崎貞治氏は桐生織染色部門の伝統工芸士として、染色技術の発展と伝承に邁進しました。2014年より屋号を桐染と改め、長く培ってきた技術による手染めの魅力を伝えたいという思いを、オリジナルブランドを通して発信しています。
| 商品 | 価格(税込) | 在庫 | 個数 | |
|---|---|---|---|---|

【受発注】杉の下駄 ※4月中旬頃発送予定(23〜25cm)
送料:一配送660円・11,000円以上で送料無料(一部地域除く)
|
¥8,800(税込) |
✕
|
販売終了 |
カートに追加されました
【受発注】杉の下駄 ※4月中旬頃発送予定を見た人はこんなアイテムも見ています
-
Nuovo Nicar(ヌオヴォニカール)
レザーサンダル W1648 CUOIO¥14,850(税込)
-
pcnq(パークニック)
【別注】ハット beats¥14,300(税込)
-
TAMPICO(タンピコ)
JUNIOR BAG XS(ジュニアバッグ)¥26,400〜(税込)
-
能登上布 YAMAZAKI NOTOJOFU
扇子¥19,800〜(税込)
-
能登上布 YAMAZAKI NOTOJOFU
ストール¥25,850(税込)
-
Have A Look(ハブアルック)
ブルーライトカットあり リーディンググラスDiva Green¥7,480(税込)
-
000(トリプル・オゥ)
グラスホルダー¥5,500(税込)
-
TRICOTE(トリコテ)
ギャザーバッグ¥18,700(税込)
-
ONEIL OF DUBLIN(オニール・オブ・ダブリン)
マキシ丈キルトスカート¥26,400(税込)
-
ROSENDAHL(ローゼンダール)
ARNE JACOBSEN 腕時計 mina perhonen BANKERS¥40,700(税込)
-
上出長右衛門窯(かみでちょうえもんがま)
招猫 鈴なり¥9,900〜(税込)
-
FilMelange(フィルメランジェ)
スウェットスカート HARRIETT¥24,200(税込)























%20MILK.jpg)












.jpg)


































.jpg)










.jpg)

.jpg)